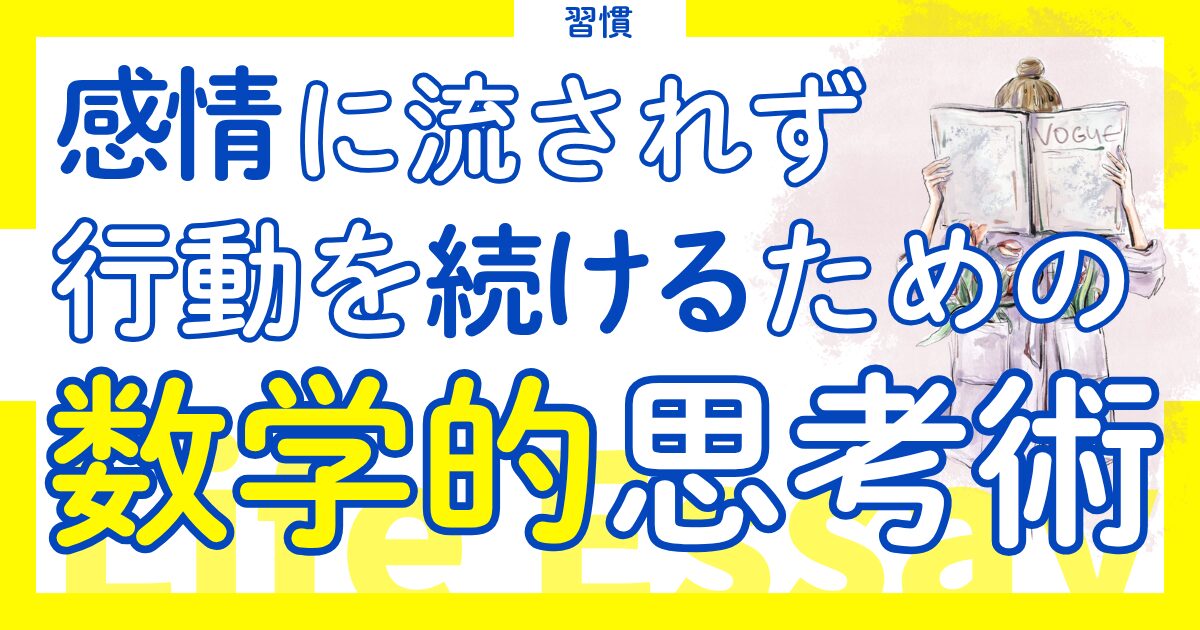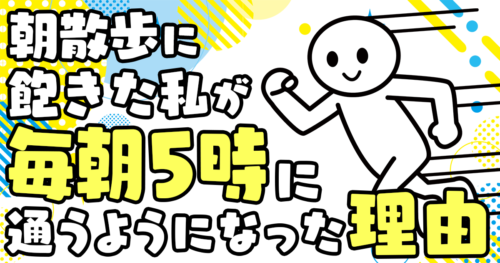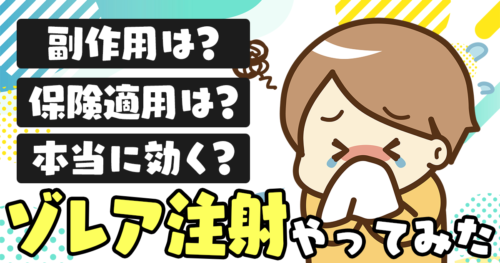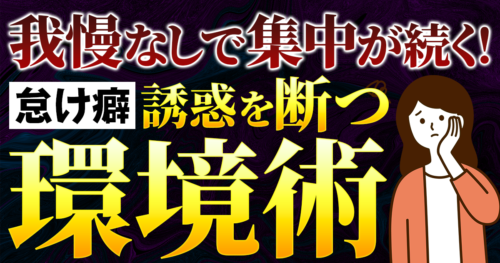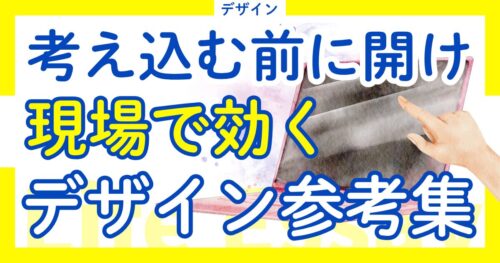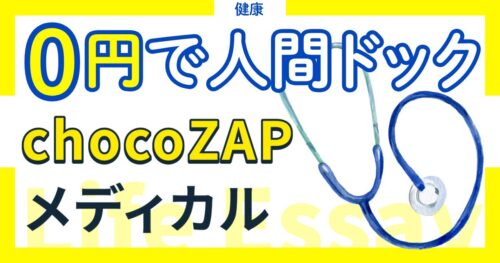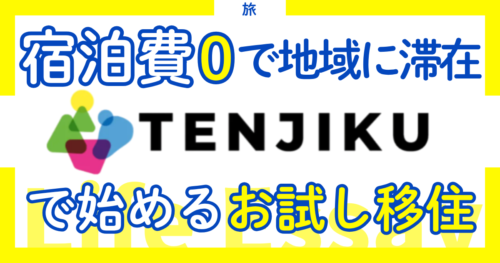「あれもこれも」で、結局何も進まない日々に、うんざりしていませんか?
やる気はある。でも、いざ行動しようとすると、気持ちの波に飲まれて途中でストップしてしまう。
実は私自身、ずっとこの繰り返しでした。そして、この悪循環から抜け出すために「数学的な考え方」を使ったんです。
これは、難しい論理の訓練ではありません。日々の生活をスッキリ整理し、「よし、今日もやれた!」と行動を止めずに継続するための、超・実践的なツールとしての数学です。この記事では、私がどうやって感情に振り回されるサイクルを断ち切ったのか、その秘密を紹介します。
行動が続かない原因は、感情ではなく構造にある
「やることが多すぎて、どこから手をつけていいか分からない!」と立ちすくんでしまう。
この状態って、本当に頭の中がぐちゃぐちゃになりますよね。私も以前はそうでした。タスク管理アプリをいくつも試しては、結局どれも使いこなせず放置。焦りだけが増して、肝心な行動はちっとも進まない。結果、時間も体力も、やる気さえも無駄にすり減らしていました。
感情に流されるのは、あなたの「意志」が弱いからではない
「どうして自分は続かないんだろう…」と、感情に振り回されては自己嫌悪に陥る。このサイクル、本当に辛いですよね。
でも、安心してください。行動が続かない人の多くは、意志が弱いわけではありません。ただ、「感情に引っ張られてしまう構造」を持ってしまっているだけなんです。
言うなれば、情報整理の仕組みがまだ整っていないだけのこと。私もその仕組みを整えるまで、ずっとこの無限ループの中にいました。
数学的思考で、「考え方の順番」を変えてみる
この悪循環を断ち切る鍵が、「数学的思考」です。
ストラテジーのアルゴリズム化(手順書)
① draw a figure, diagram(絵図を書く)
② inductive thinking(帰納的思考)
③ analogy(類推)
④ fewer variables(変数を少なくする)
⑤ specialization, generalization(特殊化,一般化)
⑥ reformation(再形式化)
⑦ auxiliary problem (補助問題)
⑧ divide into cases(場合分け)
⑨ go back to definition(定義に戻る)
⑩ set up equations(等式を作る)
⑪ indirect proof(間接証明)
⑫ work backwards(逆向きにたどる)
⑬ symmetry(シンメトリー)
⑭ logical reasoning(論理的推論)
引用元:発見的方法に基づく問題解決方略の指導に関する一考察
なぜなら、数学には「考える順番」を整理するための14の型(ストラテジー)が詰まっています。私はこれを、毎日の行動設計に応用しています。
例えば、まず「現状を図に描く(draw a figure)」ことから始めます。頭の中のモヤモヤを可視化。
それから、「小さく観察して法則を見つける(inductive thinking)」。私の場合、「朝の行動が乱れる日って、必ずスマホを早く触っているな」と気づきました。そうすれば、「変数を減らす(fewer variables)」、つまり「朝のスマホ」をサッと取り除くだけで、劇的に効果が出ます。
問題が複雑でどうしようもなくなったら、「定義に戻る(go back to definition)」。行動の基本原則を再確認することで、すぐにブレない基準を立て直すことができます。
「人生の計画」に応用できる思考の型
この思考法は、日々のタスクだけでなく、もっと大きな「人生の計画」にも役立ちます。
例えば、老後資産の計画。多くの人は「毎月いくら貯められるか」から考えがちですが、この思考法では「目的から逆に考える(work backwards)」です。つまり、「必要な生活費」と「健康でいたい期間」を明確にし、そこから逆算して、今の投資や支出を整理する。
この逆算思考に変えてから、「やらなきゃ」という無理な義務感ではなく、目的意識を持って積立を継続できるようになりました。
さらに、「論理的に確認する(logical reasoning)」という習慣を持つと、漠然とした将来の不安がスーッと減ります。数字という根拠が、あなたの判断を揺るがないものにしてくれるからです。
向いている人・向かない人
この「数学的思考法」が特に合うのは、「感情の波より、しっかりした構造で動きたい」と願っている人です。
感情の起伏が激しい人ほど、行動の「型」を持つことで、むしろ安定感が増します。逆に、「考えるより、とにかく直感で進めたい」というタイプには向かないかもしれません。
この思考の整理は、一度作り上げると、何度でも使い回しができる「再現可能なスキル」になるんです。
まずは「図」を描いて、行動を「絞る」
難しく考える必要はありません。まずはたった2つのステップから始めましょう。
1枚の紙に、頭の中を図で描く
家計でも仕事でも、今抱えている問題をざっと見える化してみましょう。
行動を3つまで絞る
手を付けるべきタスクを、まずは最重要の3つに限定してください。
この2つだけで、あなたの行動の継続率はグンと上がります。思考がスッキリ整理できれば、行動は自然とブレなく安定していきますよ。
よくある質問
- 数学が苦手でも使えますか?
-
計算ではなく「考える順序」を整理する方法なので、数式は不要です。
- どんな分野に応用できますか?
-
投資計画、健康習慣、タスク管理、人間関係の整理など、判断が多い場面で有効です。
- 続けるコツは?
-
「1日1回、思考を見える化する」。これだけで十分です
まとめ
数学的思考とは、人生の複雑な問題を「分解し、組み立て直す」ための強力な技術。考える力を鍛えることは、結果的に「生きる力」そのものを長く、豊かにすることにつながるのです。