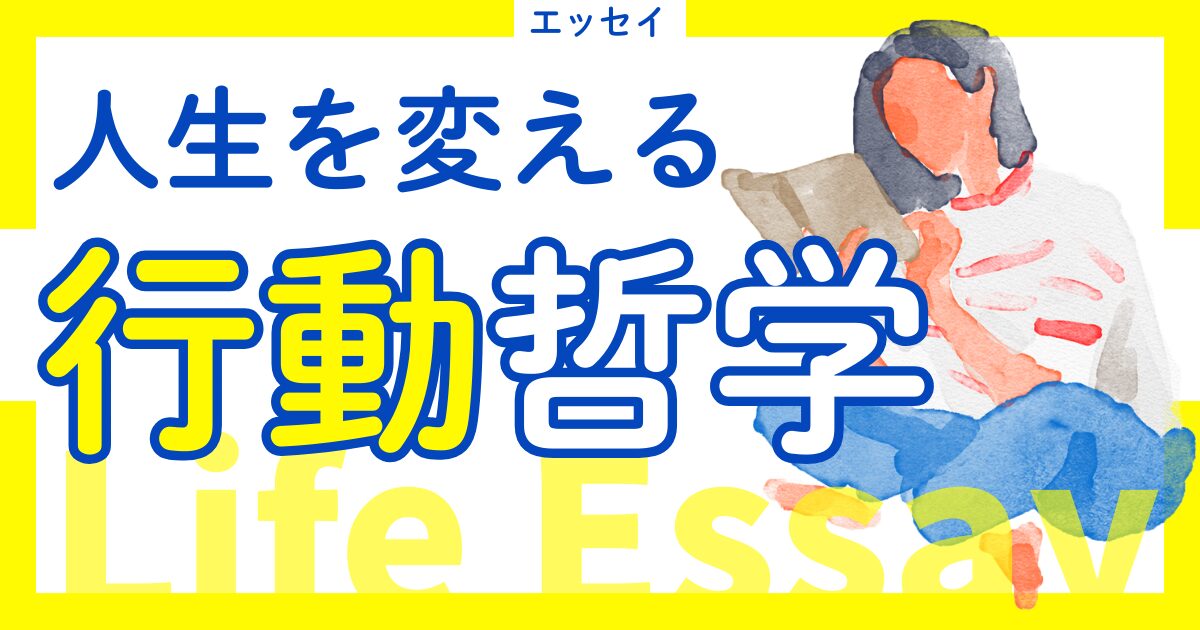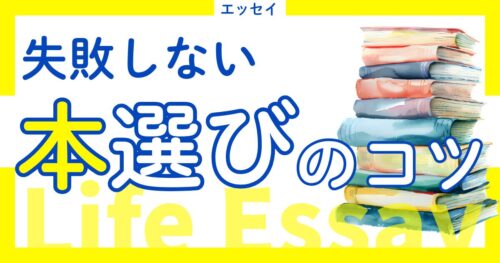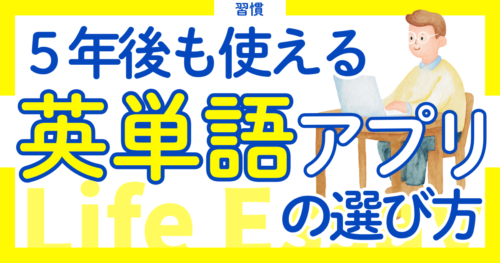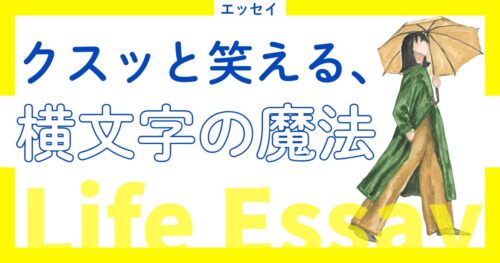人は、目に入るものすべてに対して、無意識にジャッジを下してしまう。ついX(旧Twitter)を開いてしまい、そこで目にした他者の投稿や、プロの文章に対して、「これでは少し足りない」「もっと違う切り口があるはず」と、気づけば心の中で批評している。
なぜ私たちは他人を批判するのか。それは多くの場合、自己防衛や、投影という心の働きなんです。自分の持てないスキルや目を背けたい弱点を相手に映し出して、批判することで優越感を得たり、安心しようとする。この絶え間ないジャッジの根底には、結局、自分自身への自信のなさが隠れていたのかもしれません。
しかし、夏目漱石の『学問のすすめ』にある「人の仕事を見て『たいしたことないな』と思ったら、自分自身でその仕事をやってみなさい」という言葉は、このネガティブな衝動を才能として肯定してくれました。
後進の若者たちよ、この場を借りて忠告しておきます。
人の仕事を見て「たいしたことないな」と思ったら、自分自身でその仕事をやってみなさい。
人の商売を見て、下手だと思ったら、自分でその商売をやってみなさい。隣の家の家族を見て教育がなってないと思ったら、その教育を自分の家族にやってみなさい。
人の著書を評論したいと思うなら、自分で筆を執って本を書いてみなさい。学者を評価しようと思ったら学者になってみなさい。医者を評価しようと思ったら医者になってみなさい。
大きな問題から小さな事柄に至るまで、他人の「働き」にくちばしを挟みたいと思うなら、試しにその身をその「働き」の地位において、自分自身で体験した上で考えてみなさい。
仮に職業としてまったく違うものであっても、よくその「働き」の難易・軽重を測るのです。まったく種類の違う仕事であっても、ただ両方の「働き」をもって自分と他人を比べれば、大きな間違いはないでしょう。
(明治九年八月出版)
「あなたには、より良くできるセンスがある」。問題は、その批評眼というエネルギーを、他人への批判ではなく、自分への行動に変えること。
この重たい最初の一歩を動かすため、私は山本五十六の「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」という教えを自分に課し、脳を騙すことにしました。それが「5秒ルール」と「ズーニンの法則」です。
行動を始める直前の5秒で思考を強制的に停止させ、作業のトリガーを引くのが5秒ルール。そこから最初の4分間を乗り越えれば、脳の側坐核が活性化し、意欲を高めるドーパミンが分泌されて集中力が持続する(作業興奮)というのがズーニンの法則です。他にも、ツァイガルニク効果やマイクロゴール設定にも共通しますが、要は小さな行動が次の行動を呼び込むということ。私たちはモチベーションに頼るのではなく、脳を騙して「やる」から「やれる」に変えられるんです。
批評家として鋭敏なあなたの才能を、ただの机上の空論で終わらせてはいけません。他者を的確に評価できるということは、あなた自身に、それを上回るポテンシャルがある証拠。
やる気は「作業の後に」必ず湧いてくるという心理を信じて、まずは動いてみましょう。最初の5秒で不安な思考をシャットアウトし、続く4分間だけは「ウォーミングアップ」だと割り切って手を動かしてみてください。
「4分を制する者は人生を制する」という言葉の通り、その小さな一歩が、きっとあなたを批評家ではなく、実践者へと変えてくれます。