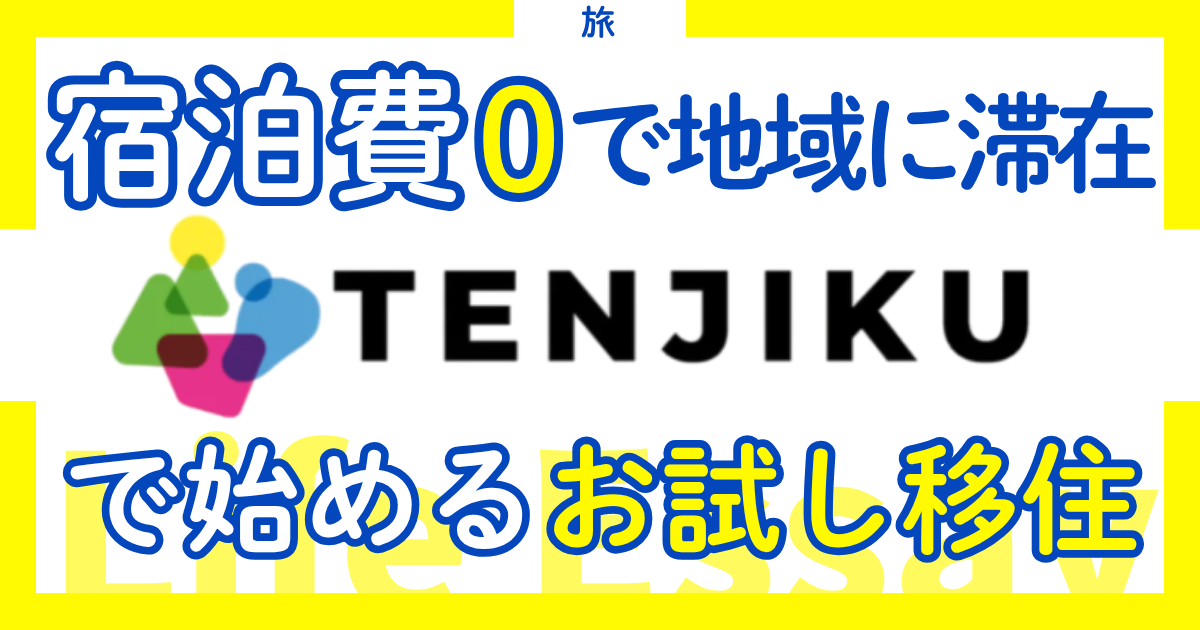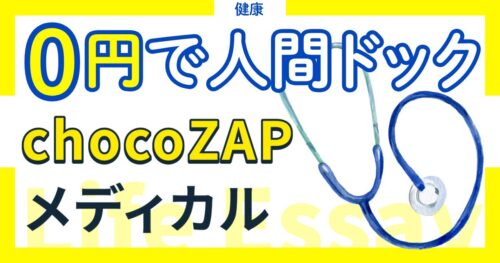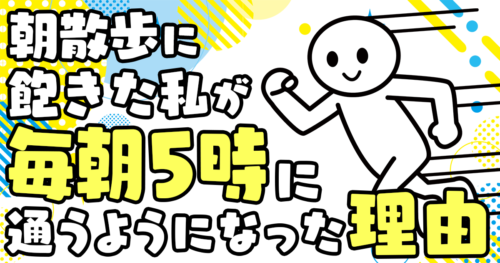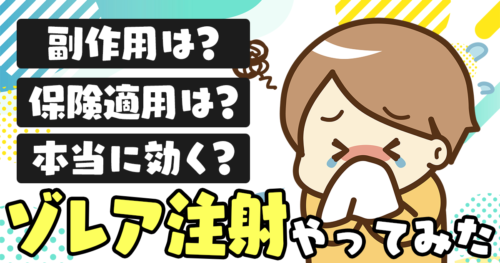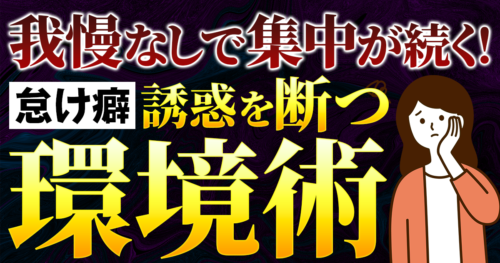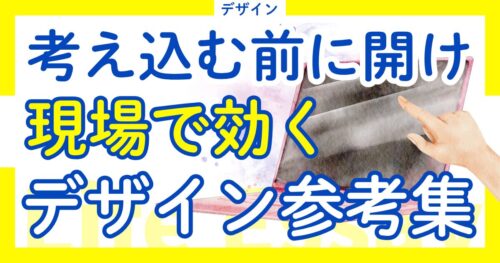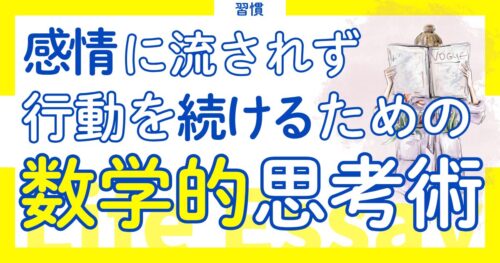観光地を巡るだけの旅行もいいけれど、「もう少しその土地の暮らしを感じてみたい」と思うことがありますよね?
私がそう思うようになったのは、都会での生活に少し息苦しさを感じていたからです。人の多さやスピードの速さに疲れ、「一度、田舎でのんびり考える時間を持ちたい」と思うように。
ちょうどコロナ禍以降、仕事が完全在宅になったことで、どこで働くかを自分で選べるようになりました。「今なら行ける」と思い、少し長めの滞在を探していたときに出会ったのが「TENJIKU(テンジク)」というサービスです。

TENJIKUは、旅人が地域に滞在し、地域の“ミッション”と呼ばれるお手伝い(1日あたり2〜4時間)をすることで宿泊費が無料になる仕組みです。「ローカル体験を通して地域を知る」というコンセプトに惹かれ、私はすぐに登録しました。
TENJIKUを活用して地域に滞在する方法を知る
TENJIKUの使い方を簡単に説明します。
まず、SAGOJOのウェブサイトで旅人登録を行い、参加可能な地域拠点を選びます。滞在中に地域が提示する「ミッション」=1日あたり2〜4時間程度の地域のお手伝い(例えば宿の清掃、イベント補助、PR活動など)をこなすと、宿泊費が無料になる仕組み。
TENJIKUを使うと、観光ではなく「暮らし」に近い形で地域に関わることができます。
私はこれまでにTENJIKU秩父、TENJIKU日光、茨城県神栖市の海のある暮らし『SET&(セッテン)』の3か所を訪れました。旅の記事は、また別日に公開したいと思います。
「地域で暮らしてみたい地域で暮らしてみたい」「将来の移住候補地を探したい」「リモートワーク拠点を探している」という人には、宿泊費を抑えながら地域と関わるこの仕組みが有効です。
たとえば、フリーランスとして在宅で作業をしながら、夕方には地域の人と会話したり、地元の飲食店を訪れたりすることで、「暮らすように滞在する」体験が可能に。
また、オーナーや地域協力隊のメンバーが地域紹介をしてくれることも多く、観光客としてでは得られないローカルな情報も得られました。
私はこのサービスを利用して、無理のない形で地域の生活に触れられました。宿泊費を気にせず滞在できる点も大きく、旅を続けながら暮らしを考えるにはちょうど良い方法だと感じています。
TENJIKU滞在で得られるリアルな地域との関わり
実際にTENJIKUを利用してみると、地域の人との距離が近づくのを感じました。私は人混みが苦手なので、いつも平日に滞在しています。イベントが少なく静かな時間が流れる中で、地元の人とゆっくり話す機会が増えました。お手伝いの内容はトイレ掃除と部屋の片づけ程度。それでも、ちょっとした会話の中で「どこから来たの?」「ここのお店がおいしいよ」と声をかけてもらえるのがうれしい。
観光では数時間で通り過ぎるような場所でも、数日滞在すると地域の“日常”が見えてきます。朝の通学路、商店街の開店時間、夜の静けさ。そうした当たり前の風景の中に、人の生活があります。私は、TENJIKUで過ごす時間が“観光地を見に行く”から“地域で過ごす”に変わる感覚を得ました。
この経験を通して、「暮らしを体験する旅」という新しい価値を実感しました。
なぜTENJIKUが旅と地域をつなげるのか
TENJIKUが多くの人に選ばれる理由は、地域との関わりを前提に設計されている点にあります。
TENJIKUを運営するSAGOJOは、地域の課題を“ミッション”として構成し、旅人がそのミッションを通じて地域と接点を持つことを目的としています。
例えば、宿泊費が無料になる条件として「地域のミッション参加(1日2〜4時間)」が設定されており、この形が“単なる旅行”ではない“地域滞在”を実現しています。
地域協力隊、地域の案内人、施設運営者が旅人を受け入れ、地域の生活に近い滞在を可能に。滞在を終えても、地域とのつながりをSNSで維持したり、別の拠点で再度訪問したりする旅人が多いという記事もあります。
この仕組みはお金が直接発生しないからこそ、旅人も地域もお互いよい交流にすることに自然に焦点があたっていて、相互に未知との出会いによる刺激と変化が起き、まるで仲間のような人と人とのつながりができているように感じるという。
旅人は同じ地域に来ても、ミッションの内容や場所が違い、出会う人が広がるなど、様々な視点で地域に触れることができる。実際、旅人としての滞在をきっかけに移住した人も現れており、通っているうちに地域の人を知り、リアルな情報が入り、場合によっては家や仕事まで関係性の中から得たケースもあるという。
そして地域側にとっては、旅人が自分たちの地域を好きになって何度も来てくれる、喜んでくれることで誇りが醸成され、地域内の再発見につながり、希望にもなっているのではと。引用:https://www.tourism.jp/tourism-database/viewpoint/2024/07/boundary-02/?utm_source=chatgpt.com
こうして、旅が終わっても“地域との関係”が残る仕組みとして機能しており、単なる観光では得られない持続的な体験を提供しています。
TENJIKUを使う前に知っておきたい3つの注意点
TENJIKUを使う前に、いくつか知っておくと安心なポイントがあります。
まず、拠点によって設備や環境が異なります。Wi-Fiが弱い場所もあるようですが、私は今のところ不自由を感じたことはありません。ただし、ネットを使った仕事をしている方は、滞在前にオーナーさんへ環境を確認しておくのがおすすめです。
TENJIKUの施設は「観光宿」ではなく「地域の拠点」なので、設備や周囲の環境も地域ごとに違います。
また、平日は地域のイベントが少なく、人と関わる機会が限られる場合もあります。
静かに過ごしたい人には向いていますが、「地元の人と交流したい」「イベントに参加したい」という方は、土日に合わせて滞在を計画するとより充実します。
そして最も誤解しやすい点が“報酬”です。
TENJIKUは「お手伝いをする代わりに無料で宿泊できる」という仕組みで、金銭的な報酬は発生しません。
お手伝いはあくまで“地域に関わる体験”であり、雇用契約に基づく仕事ではありません。
その分、地元の人との会話や日常への参加など、“暮らしの一部に入る体験”ができます。
観光でも労働でもない「地域との関わり方」として捉えると、TENJIKUをより心地よく活用できます。
旅をしながら暮らしてみたいときは、TENJIKUを使ってみましょう
「旅をしながら暮らしてみたい」「地域での生活を体験してみたい」と思ったときは、TENJIKUを試すのが一番です。
登録も簡単で、SAGOJOユーザーなら誰でも無料で宿泊できます。地域に関わりながら、現実的なお試し移住を体験できます。
都会の生活が忙しく感じたとき、環境を変えるだけで視点が変わることがあります。
TENJIKUは、観光でも移住でもない“中間の旅”を体験できるサービスです。私も、この仕組みを通じて暮らし方の選択肢が広がりました。これからも気になる地域を少しずつ訪れ、自分に合った生活を探していこうと思います。